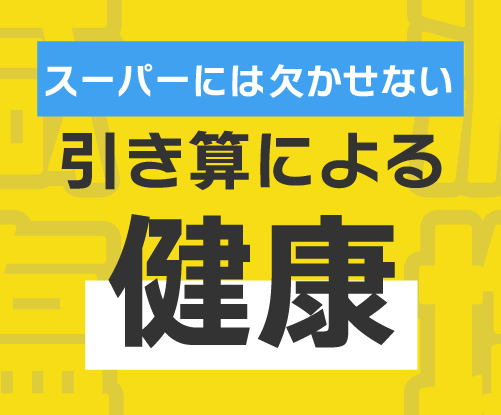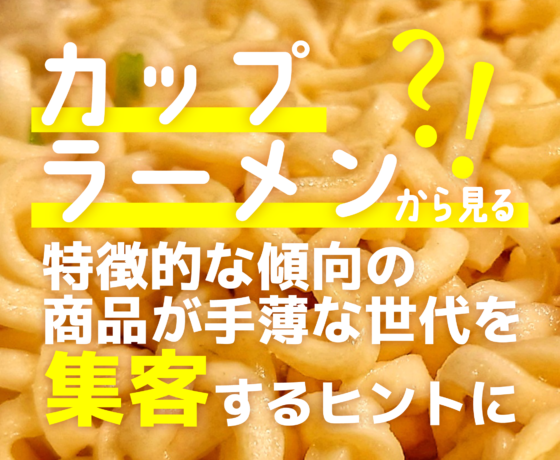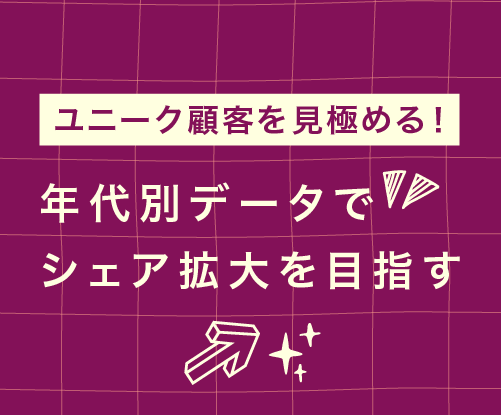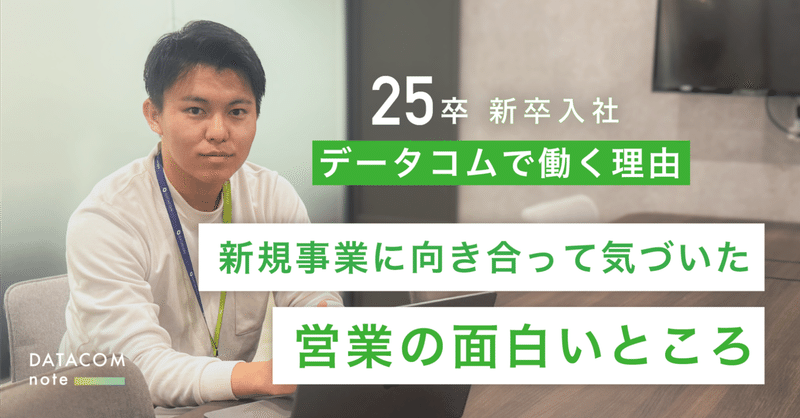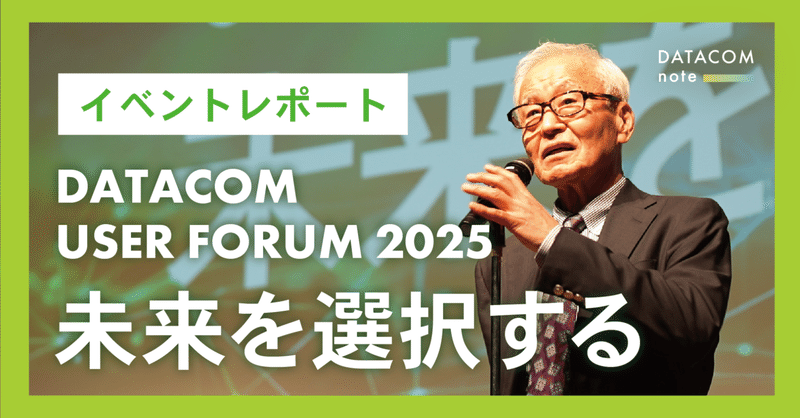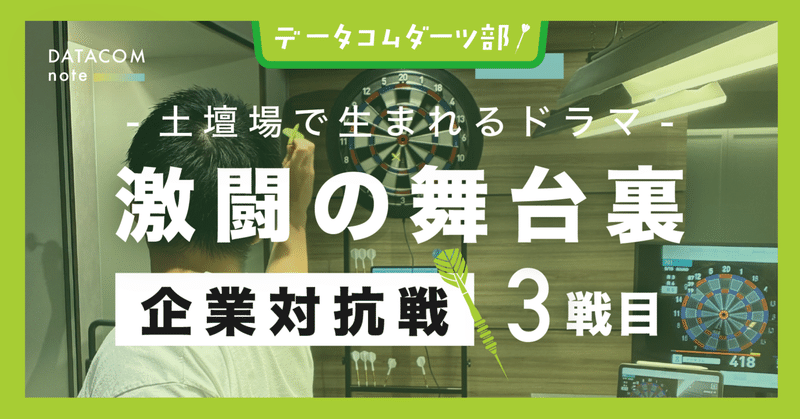同時購買データで見えてくる!人気メニューと野菜の関係性

野菜の購買行動を分析すると、食べられる頻度だけでは見えてこない「食卓での役割」が浮かび上がります。そのカギを握るのが「同時購買データ」です。どの野菜がどの食材と一緒に買われるかを可視化することで、顧客が実際にどんなメニューに利用しているのかが分かります。これは単に数字の相関関係ではなく、販売戦略を考えるうえで極めて有効なヒントとなります。
相関が強い野菜は「定番メニュー」に組み込まれている
同時購買の相関が強い野菜は、食卓での位置づけが明確です。たとえば、ごぼうは乾燥椎茸やこんにゃくと一緒に購入される確率が高く、煮物やすき焼きといったメニューに組み込まれていることが容易に推測できます。逆にもやしの場合は、中華麺や焼きそば用のソースと強く結びついており、1.5〜2.6人に1人という高い割合で同時購買が発生します。安価で汎用性が高いもやしが、購買頻度ランキング上位に入る理由も納得できます。
同様に白菜は鍋つゆや鍋用スープとほぼ一体で購入され、用途が極めて明確です。きのこ類も種類によって関連メニューが異なり、椎茸はすき焼き、エリンギは焼肉、えのき茸は鍋料理といった具合に、消費者の調理行動とリンクしています。
相関が弱い野菜こそ売り場提案が必要
一方で、同時購買の相関が弱い野菜もあります。ほうれん草やかぼちゃのように単独調理で食べられる野菜は、関連商品が出にくい傾向にあります。レタスやミニトマトも、サラダ以外の用途が明確でないため、データ上は相関が薄くなりがちです。しかし近年ではタコスやアクアパッツァなど、海外料理の普及に伴い、新しい関連性が浮上し始めています。
新しい食べ方や料理の提案ができれば、相関する商品が増え、買上点数も自然と増加するはずです。一方で、旬の季節しか売り場に並ばないものや、希少性が高くあまり目にしないものは、売り手側が何もしなければそのままになってしまいます。
おすすめ料理の提案で関連購買を増やす
例えば、カブやズッキーニ、フキといった野菜は、普段あまり料理をしない人が手を出さない野菜と言えます。これらはデータでも同時購買率が著しく低く、ほとんど関連が見られません。こういった商品こそ、おすすめ料理の提案を地道に続ける必要があり、手間抜きの発想が必要な商品です。カブであれば、関東圏限定ではありますが、”ほうとう”が高い同時購買確率で出てきます。このようなメニューを提案することで相関する商品を増やし、結果的に売上全体を底上げできる可能性があるのです。
結論として、同時購買データは「売れる野菜」と「埋もれる野菜」を明確に切り分けてくれます。データが示す消費行動をヒントに、新しい料理提案や関連販売を仕掛けることが、野菜売場の活性化に直結します。