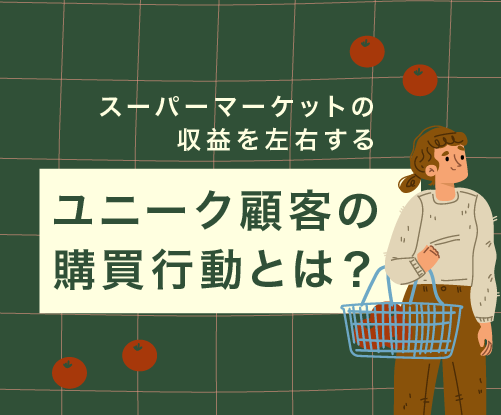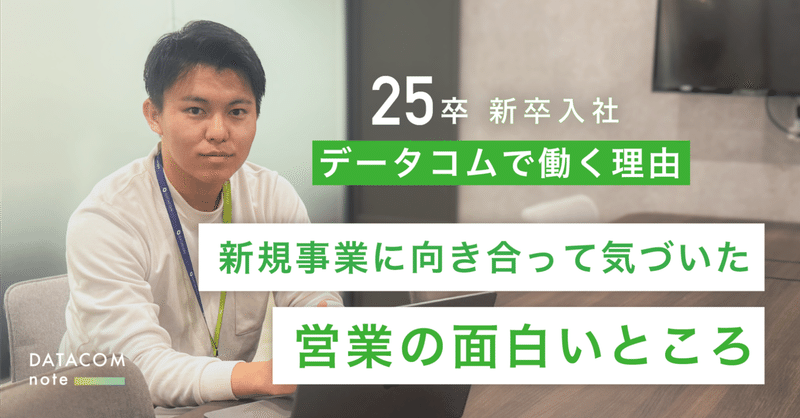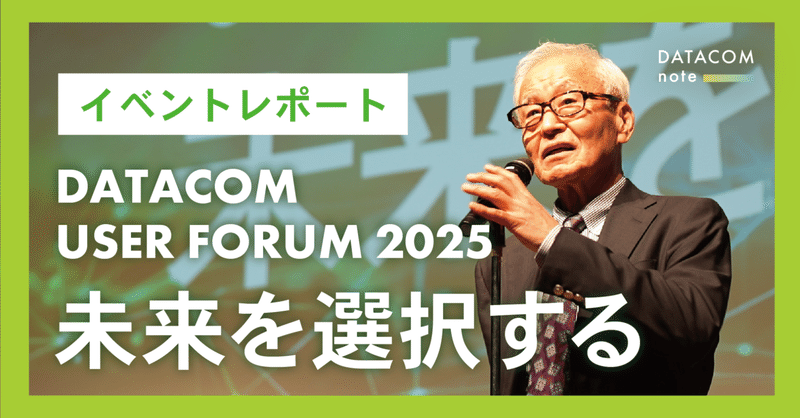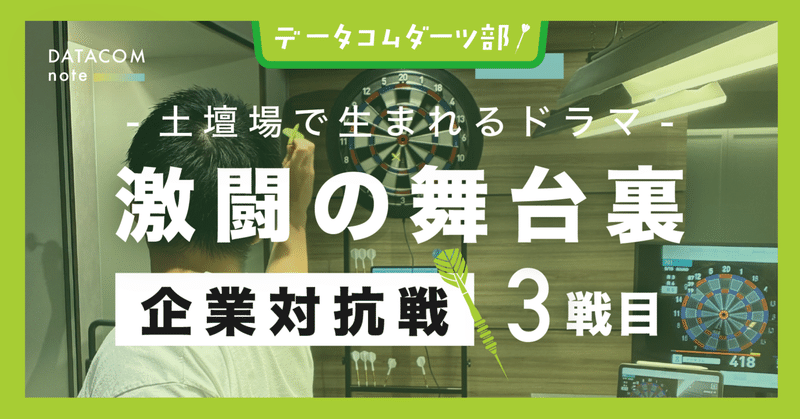買い手が「何も知らない」を前提に!POPで防ぐ野菜の機会ロス

野菜の購買頻度を見てみると、断トツで1位は「サラダ用カット野菜」です。洗う必要すらなく、そのまま食べられる手軽さは、多くの人に支持される理由です。実際、リピーターも多く、日常的に利用する人が少なくありません。一方で、調理方法が分からない、使い切れるか不安、といった理由から購買に至らず、販売機会を逃している野菜も数多く存在します。これが「機会ロス」です。売場で放置されれば、潜在的な需要は永遠に顕在化しません。こうしたロスを埋めるためには、「買い手が何も知らない」前提で訴求を設計することが重要になります。その代表的な手段が、POPによる情報提供です。
機会ロスは「知らない」ことで生まれる
「機会ロス」という言葉は、通常は品切れや棚に商品が見つからない状況を想起するかもしれません。しかし実際には、消費者が食べ方や調理の仕方を知らないために購買を諦めるケースもまた、深刻な機会ロスです。しかも、在庫管理のように数字でチェックできないため、売場で見逃されやすいのが実態です。
消費者の視点で見ると、野菜の場合、まずは生で食べられるかどうか。そうでなければ、ゆでるのか、炒めるのか、炒める時は何と一緒に炒めたらいいのかなど、分からないことはいくらでも出てきます。
知らないことを前提とした訴求が必要
たとえば「そうめんかぼちゃ(金糸瓜)」を売場で見かけたとしても、「珍しいけれど食べ方が分からない」という理由で多くの人は手を伸ばしません。生キクラゲも同様で、「卵と炒める」といったシンプルな調理提案をPOPで伝えなければ、知っている一部の人しか購入しないでしょう。さらに春の定番である菜の花でさえ、「あく抜きの為に下茹でが必要」と誤解されていることが多く、その煩わしさが購買意欲を削いでいます。このような状況であれば、例えば「パスタにそのまま使える」など、迷っている顧客の背中を押す一言を添えることが大事ではないでしょうか。
特に、旬の時期しか売場に出ない野菜や山菜類は、同時購買データを見ても関連商品がほとんど出てこないか、確率が著しく低い傾向があります。つまり「知られていないから売れない」という構図がはっきりと浮かび上がるのです。
POPが果たす重要な役割
だからこそ、POPは単なる商品名の表示ではなく、「買わない理由をつぶすツール」として機能させるべきです。例えば「そのままサラダに」「パスタに和えるだけ」「下処理不要」など、一言添えるだけで購買行動は変わります。迷っている顧客の背中を押すその一言が、売上を左右するのです。このような小さな工夫の積み重ねが、顧客の購買頻度と買い上げ点数を伸ばすことにつながります。