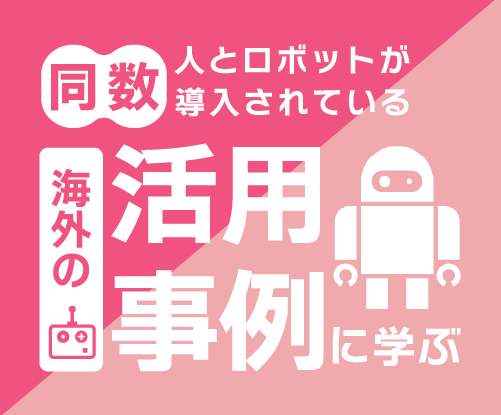オンライン上に有益な機能を構築し継続的な顧客との接点を創ろう~最先端アメリカのリテーラーに学ぶ取り組みの実際~(後編)

リテールメディアにビジネスとして取り組むには、多くのことを考える必要があります。
データを活用するためには顧客からの"信頼"が最も重要になりますし、
オンライン上に効果的に顧客との接点を創ること、そして売場を広告効果の高い場にする工夫も必要です。
今回は、海外リテーラーの取り組みを参考にしながら、成功の鍵について考えます。
本ブログは前回の続きになりますので、VOL.1を読んでいない方は以下からご覧いただけます。
日本流リテールメディアの取り組み方
リテールメディア後進国となってしまった日本ですが、
どのような取り組みであれば、今後広がりを見せる可能性があるのでしょうか。
まず、オンライン上での接点創出は必要不可欠です。
実は、日本とアメリカにおける食品関連 EC 化率は 3% 前後と同水準です。
従って、
"オンライン購買の規模が圧倒的に異なるから、アメリカでリテールメディアが成立している"
という言い訳は成立しないわけです。
では、なぜアメリカではうまくいっているのか。
それは、オンラインとオフラインの世界がうまくシンクロしているからだと感じます。
アメリカの小売業では、アプリやネットストアがしっかりと整備されています。
家にいるときであれば、牛乳、卵、ティッシュペーパーなど普段から利用している商品を注文したり、
お得情報や製品情報を取得したりするために利用します。
また、店舗を訪れた際には、店内マップを開いて売場を探したり、チェックしておいたクーポンを確認し、提示したりするために利用します。
このように、購買の瞬間のみならず、各所で接点が生まれるような工夫がなされているのです。
近年は有償・無償のさまざまなロイヤルティプログラムが構築され始めており、
プログラムによっては、動画ストリーミングやガソリンの値引きなど、
オンライン・オフライン問わず自社の買物と直接的なつながりがないようなものまで提供しています。
それは、アメリカの小売業が自社の顧客を一人の生活者として捉え、どんなサービスを提供したら利便性が高まり、
かつ自社との結び付きが強くなるかを熟考しているが故です。
従って、リテールメディアの取り組みにおいて、日本の小売業が意識すべきことの 1 つ目は、
顧客が利用したくなるようなオンライン機能を構築して継続的な接点を創ることです。
紙カードやクーポンをオンライン上に移行しただけのアプリでは、普段開いてもらえないのも当然です。
人が集まる媒体にならない限りは、"メディア"として広告収入を得られないということを忘れてはなりません。
顧客が利用したくなる機能をどのように創るかが肝なわけですが、
小売業、特にスーパーマーケットやドラッグストアであれば、生活者の食や健康に関わる知見を活かすことが近道ではないでしょうか。
普段の生活における困り事を解決するような情報や健康管理機能などの提供が充実していれば、
生活者との距離はぐっと近づくように思います。
そのとき、"関連性"の高い商品やサービスの広告をひも付けることは有益でしょう。
この"関連性"、英語にすると"relevant"というのが二つ目のポイントです。
アメリカの小売業向けカンファレンスでリテールメディアが語られるときには、
必ずと言ってよいほど、この"relevant"への言及があります。
アメリカの小売業は、顧客から取得するデータを活用して、マネタイズを図る上で、
顧客からの"信頼"が最も重要になると考えています。
登録された属性情報や購買履歴を正しく読み取れば個々人を精緻に理解できるにもかかわらず、
中途半端なロジックで商品を提示してしまうと、顧客の心は一気に離れていきます。
顧客自身もデータを取得されていることを認識しているからこそ、テレビ・Web 広告以上に求められる水準が高いのです。
世界最大手スーパーマーケットチェーンの一つであるカルフール社はそのことを非常に強く意識している企業です。
多大な研究やテストの甲斐あって、同チェーンでの購買3回目以降から、購買商品の 70% を予測することが可能になったと言います。
ここで主張したいのは、このくらい強い意識を持って顧客とのコミュニケーションを取らなければ、
リテールメディアの繁栄は難しいということです。
ビジネスである以上、小売あるいはメーカーが自社の意向で強く打ち出したい商品があるのは当然です。
ただし、的外れなターゲットに訴求したところで、誰もメリットはないでしょう。
そのため、理想を言えばデータ分析・AI、およびデジタルならではのコミュニケーションに長けた人材を強化することが必要です。
しかしながら、一朝一夕にそのことをかなえるのは難しいでしょう。
そこで、大切になってくるのが、素直に"顧客に聞くこと"ではないかと思います。
ある程度のロジックによって、各顧客に提示すべき商品が導き出されたら、まずはためらわず提示します。
その後で大切になってくるのが、その商品に対する声・反応の取得と改良です。
現状は、提示後に買われたか否かで有用性を測っているでしょうが、それでは次につながりません。
Amazon社が手掛けるアパレルショップの"Amazon Style"は、そういった状況を打破する取り組みを行っています。
Amazon といえども、初回あるいは数回目の買物において、顧客に最も適した商品を提示するのは困難です。
そこで、同店では提示した複数の商品に対して、顧客からレビューを得る仕組みを取り入れています。
アプリおよび試着室に設置されたスクリーン上で、提示された商品の好き嫌いを選択していくと、
徐々に相性の良い商品がレコメンドされるようになっていきます。
数分の間で最適化されていくのは、さすが Amazon という感じではありますが、日本の小売業も見習うべきポイントではないでしょうか。
購買以外の"好意度"などを取得できるのが、オンラインならではの利点ですので、
まずは小さく取り入れていく必要があると思います。
ここでもデータ分析・AI の力は必要になってきますが、やみくもに最適解を探すよりも顧客の声・反応に従う方が近道です。
ここまで言及してきたことを意識しながらアプリやネットストアを構築していくことで、
個々人に適したオンライン上の"メディア""売場・棚"に仕上がり、
人が集う、すなわち広告効果の高い場となっていくでしょう。
最後に、オフライン型のリテールメディアとして、日本でも広がりを見せつつあるサイネージに触れたいと思います。
日本ではリテールメディア≒サイネージという認識が強かった時期もありましたが、
リテールメディアのごく一部であることを再度理解すべきです。
売場というラストワンマイルでコミュニケーションを取れる媒体としては優れていますが、
売場で顧客が視聴する長さは非常に限定的。
筆者が行った検証によると、長くても 5 秒前後です。
また、視聴率(1 秒以上の視聴者/サイネージ前通行者)も 1 桁台です。
カテゴリーによっては、設置後に 120% 程度の売上伸長効果がありますが、
売場用の超短尺コンテンツを作ったり、小売別の CMS に入稿したりする手間を考えると、
低単価の食品・飲料などにおいては、決して高い効果とは言えないでしょう。
また、オンライン上のリテールメディアとは異なり、広告接触者を個別にトラッキングできないので、効果計測の難しさもあります。
そういった背景からか、アメリカのスーパーマーケットでサイネージを見かけることはほとんどありません。
ただし、この所感はその場での売上を効果として捉えた場合であり、
商品の"認知"や"好意度"を押し上げることを目的にすれば話は別です。
来店客、すなわち比較的関心の高い潜在視聴者をターゲットに、自社の商品を紹介するメディアと捉え、
中期的な視点での効果を期待する方が良いのではないかと思います。
最後に
ここまで、アメリカおよび日本におけるリテールメディアの状況を考察してきました。
既述の通り、食品関連などの EC 化率に大きな差がないにもかかわらず、アメリカに大きく水をあけられています。
日本の小売業がリテールメディアに取り組む上で、最も重要なことは
「オンライン上に有益な機能を構築して、顧客との接点を創る」ことだと思います。
継続的に接点を持ち続けるためには、「関連性のある」情報や機能を提供することを怠らず、
そして「顧客の声・反応」をもって日々改良していくことが求められます。
リテールメディアは、小売業の本業とは一線を画す事業であり、一筋縄ではいかないでしょう。
店舗を軸に考えていたこれまでの発想から転換し、新たな気持ちで臨むことが、
リテールメディアを通して新収益を獲得するための第一歩となるに違いありません。
取締役 経営推進部部長 小野寺裕貴
 慶応義塾大学大学院卒。株式会社みずほ銀行での法人営業、
慶応義塾大学大学院卒。株式会社みずほ銀行での法人営業、
株式会社インテージでの事業開発・アライアンスを経て、データコムへ入社。
前職時より米国等のリテールトレンドの探求、発信を行っている。
こちらの記事は、販売革新11月号に掲載されています。
※外部サイト(Fujisan.co.jp)に遷移します。
本記事は、スーパーマーケット専門情報誌「販売革新」にて弊社経営推進部の小野寺裕貴が連載しているものであり、株式会社アール・アイ・シー社の承認の上掲載しています。
出典:販売革新2023年11月号